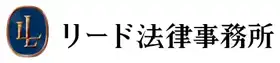解決事例 CASE
名誉毀損罪
インターネット上の虚偽の投稿について、名誉毀損の刑事告訴が受理された案件
- 事件の概要
-
A(40代男性)は、ジャズバーBを経営している。
ある時、Aは、テレビ局から取材を受け、Bを取り上げた番組が放送されることになった。
しかしながら、その後、SNSにおいて、とあるアカウントより、「昔Aから性被害を受けたことがある」などと虚偽の投稿がなされ、また、上記番組の関係者に対し、「Aから性被害を受けた」旨伝えるメールを送信した。
そのため、取材に半年以上の期間を要したにもかかわらず、Bを取り上げたテレビ番組の放送が中止されることとなった。
なお、Aは、テレビ番組のスタッフより、「性被害を受けたとの投稿が存在する以上、コンプライアンスの関係から番組を放送することができないため、投稿・メールの内容が事実無根であるならば、刑事告訴をしてほしい」と言われたため、リードに相談するに至った。
- 解決結果
- インターネット上の虚偽の投稿について、名誉毀損の刑事告訴が受理された。
- ポイント
-
本件においては、発信者情報開示請求を行い、SNSの投稿者(アカウントCの氏名・住所)を特定した上で名誉毀損罪での控訴を行うべきであるところ、上記の通り、Bを取り上げたテレビ番組の放送が中断されたほか、Aから性被害を受けたなどと虚偽の事実を流布されたことにより、Bの来客数が激減するなど、経済的に深刻な不利益を被っていたことから、当該発信者情報請求手続きを行わず、被告訴人を氏名不詳者として、告訴をすることとなった。
なお、本件においては、上記投稿を行っているアカウント名がAと付き合いのあった演奏家C(30代女性)の芸名であったことに加え、同アカウントにおいて、Cの姿態を自ら撮影したいわゆる自撮り写真が頻繁に投稿されていた事実から、警察の捜査において、犯人性(Cが上記投稿・メールを行ったこと)について疑義が生じないと考えたため、上記発信者情報開示請求手続きを省略することができた。
インターネット上の名誉毀損については、犯人性(誰が名誉毀損行為を行っているのか)が問題となるが、本件のように、本人特定につながる情報がある場合には、発信者情報開示請求を行わずとも告訴できる場合があるため、まずは弁護士に相談されたい。