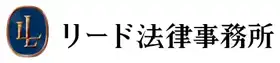解決事例 CASE
その他
元従業員がパソコンから顧客情報を持ち出した行為について、不正競争防止法違反の刑事告訴が受理された案件
- 事件の概要
-
A(60代男性)は、B社の代表取締役であるところ、ある時、同社の従業員C(40代)が、Aに無断でB社と同じ事業を行うことを目的とするD社を設立し、同社の代表取締役に就任し、その後、退職届を提出した。
Cの行動を不審に思ったAは、B社の顧客情報が記録されているサーバーを確認してみたところ、Cが同サーバーから顧客情報の一部を抽出し、また、Cの担当する顧客との間で締結されていたB社顧客間の契約をAが無断で解約されていた事実が発覚した。
Aは、CがD社の事業に用いるために、B社の顧客情報を不正に持ち出したと考え、リードへ相談するに至った。
- 解決結果
- 不正競争防止法違反での告訴が受理された。
- ポイント
-
本件においては、Cの行為について、背任罪または営業秘密侵害罪(不正競争防止法違反)に該当すると考えられたが、立証上の観点から、不正競争防止法違反で告訴することとなった。
不正競争防止法違反で告訴する場合に問題となるのは、「秘密管理性」と「犯人性」である。
まず、本件においては、B社に設置されたPCに顧客情報を閲覧するためのID・パスワードが保存されていたため、同PCを起動すれば、誰でも同顧客情報にアクセスすることができる状態にあったことが、「秘密管理性」が認められる要素となる「アクセス制限性」(情報にアクセスできる者が制限されていること)がないのではないかという問題があった。
しかし、この点について、アクセス制限性は、同じく秘密管理性が認められる要素となる「認識可能性」(情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であること)が認識できるようにされていることを担保する1つの手段であると考えられているため、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる(「認識可能性」を満たす)場合に、十分なアクセス制限が無いことのみを根拠に秘密管理性が否定されることはないとされている。
したがって、本件において、仮にアクセス制限性が認められない場合であっても、顧客情報を閲覧するためのIDとパスワードが設定されていることから、Cとしても、同顧客情報がB社の営業秘密として管理されていることを認識することができたといえるため、「秘密管理性」の要件を満たすものであると立証した。
そして、犯人性については、B社において顧客情報にアクセスすることができるのがAとCのみであったことに加え、無断で解約された顧客の担当職員がCであったこと、Cは同業のD社を設立していたことから、同顧客情報を持ち出す実益と動機があったことから、これを証明した。
警察に対して上記事実を丁寧に説明することによって、不正競争防止法違反での告訴が受理された。
顧客データを持ち出す行為については、不正競争防止法上の営業秘密侵害罪に該当する可能性があるため、従業員等に顧客データを持ち出されてしまった場合には、まず弁護士に相談されたい。