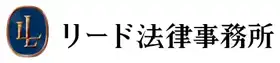横領罪の公訴時効期間は、類型により3〜7年です。期間を過ぎると、加害者を刑事裁判にかけられなくなります。加害者に刑罰を科したいのであれば、早めに動かなければなりません。
この記事では、横領罪の時効期間や起算点、時効が過ぎたらどうすべきかなどを解説しています。横領の被害を受けた被害者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
横領罪の時効
横領罪の公訴時効期間は、類型により3〜7年です。刑法に規定されている横領罪には3つの類型があり、それぞれ刑罰や時効期間が異なります。
具体的には、以下の表の通りです。
| 罪名 | 例 | 法定刑 | 時効 |
| 単純横領罪 | 友人から預かったDVDを売却する | 5年以下の懲役 | 5年 |
| 業務上横領罪 | 経理担当者が会社のお金を着服する | 10年以下の懲役 | 7年 |
| 遺失物等横領罪 | 落とし物の財布を自分の物にする | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料 | 3年 |
公訴時効期間を過ぎると、刑事裁判にかけられなくなり、犯人に刑罰を科せません。犯行の事実に気がつかなかったり、犯人が誰か知らなかったりしても、犯行の時点からカウントした時効期間が経過すると、罪に問えなくなってしまいます。
公訴時効期間の長さは、犯罪の内容や法定刑の重さによって決まります。横領の場合には、時効期間は類型によって3〜7年であり、比較的短いです。
加害者に刑罰を科すためには、早めに被害届や告訴状を提出して捜査を進めさせ、期間内に起訴してもらう必要があります。
以下で、各類型について要件や時効期間などについて解説します。
単純横領罪の時効は5年
単純横領罪の公訴時効期間は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。
そもそも単純横領罪とは、他人から管理を任されている財産を自分の物にする犯罪です。他人から預かって自分の手元にある財産を、着服、売却などしたケースで成立します。
該当する例としては、以下が挙げられます。
- 友人から預かったお金を自分の物にする
- 他人に管理を任されていた通帳から、自分の欲しい物を買うために勝手にお金を引き出す
- 友人から預けられたゲームソフトを売却する
特徴は、他人から管理を任されて手元にある物を、勝手に自分の物にする点です。管理を任されておらず、他人の占有下にあるものを奪う行為は窃盗罪にあたります。
単純横領罪に該当するのは、プライベートで管理を任されていた他人の財産を自分の物にするようなケースです。仕事で管理を任されていた財産を自分の物にした際には、次に紹介する業務上横領罪が成立し、より罪が重くなります。
法定刑は「5年以下の懲役」です。罰金刑は規定されていません。起訴されて刑事裁判になれば、必ず懲役刑が言い渡されます。
時効期間は5年です。犯行から5年が経過すると、起訴して刑罰を科すことができません。
業務上横領罪の時効は7年
業務上横領罪の公訴時効期間は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
業務上横領罪は、業務上管理を任された財産を自分の物にする犯罪です。会社の金品を管理する立場にある人が着服したケースなどで成立します。
該当する例としては、以下が挙げられます。
- 経理担当者が、会社の預金から自分の口座に振り込みをする
- 集金担当者が、取引先から受け取ったお金を持ち逃げする
- 店舗責任者が売上額を過少申告して、差額を自分の懐に入れる
ポイントは、業務上財産の管理を任されていたかです。会社の財産を自分の物にしていても、管理権限がなかったのであれば窃盗などの別の犯罪が成立します。
法定刑は「7年以下の懲役」です。業務によっては大きな額の財産の管理を任されるケースがあり被害が大きくなりやすいため、単純横領罪よりも刑が重くなっています。被害金額が大きいと、執行猶予がつかずに実刑判決がくだされ、加害者が刑務所に収監されるケースが多いです。
時効期間は7年です。法定刑が重いため期間が長くなっています。とはいえ、7年が経過すると加害者の刑事責任を追及できなくなります。
遺失物等横領罪の時効は3年
遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)の公訴時効期間は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
遺失物等横領罪は、人の手を離れた他人の財産を自分の物にする犯罪です。落とし物などを自分の物にしたケースで成立します。
例としては以下が挙げられます。
- 落とし物の財布を拾って警察に届けず、お金を抜き取った
- 放置自転車に乗り立ち去る(窃盗罪に該当する場合あり)
- 釣銭が多いことに後で気がついたが、返却しなかった
ポイントは、被害品が人の占有を離れていた物であったかです。所有者が一時的に置いていただけで、戻ってくるつもりであったときには窃盗罪になります。
他の類型の横領罪とは異なり、財産の管理を任されていないときに成立する犯罪です。「横領」と名がついているものの、他とは性質がやや異なります。
法定刑は「1年以下の懲役」「10万円以下の罰金」「科料(罰金に似ているが、金額が1000円以上1万円未満のもの)」のいずれかです。他の類型と比べると、大幅に刑が軽くなっています。
時効期間は3年です。法定刑が軽いため、時効期間も短くなっています。気がついたら早めに申告する必要があります。
横領罪の時効起算点は?
時効期間の起算点は「犯罪行為が終わった時」です(刑事訴訟法253条1項)。すなわち、犯罪行為が終わった時点から時効のカウントが始まります。
横領罪については、たとえば、
- 友人から預かったDVDを売却した時点(単純横領罪)
- 会社のお金を自分の口座に振り込んだ時点(業務上横領罪)
- 落とし物の財布を持ち逃げした時点(遺失物等横領罪)
などが時効の起算点です。
横領は繰り返し行われるケースも多いです。何度も横領行為をしたときには「包括一罪」としてまとめて扱われる場合があります。包括一罪のときには、時効の起算点は最後の行為の時点です。
たとえば、友人から3本ゲームソフトを預かり、近い日付でネット上で3人の買い手に別々に売却したケースです。行為としては3個あるものの似ており、被害者が同じで、同一の意思により犯行に及んでいるといえます。そのため「包括一罪」となり1つの犯罪として扱われる可能性があります。包括一罪であれば、時効の起算点は最後の横領行為をした時点です。
複数の横領がまとめて1つの犯罪とされるか、別の犯罪として扱われるかは状況によります。誰にでも判断できる明確な基準はありません。別の犯罪とみなされると、それぞれの横領行為の終了時点から時効期間が別々にカウントされます。
また、複数人で協力して横領したときには、最終行為が終わった時点から、全員について時効期間がスタートします(刑事訴訟法253条2項)。
なお、被害者が犯行を認識していたか否かは、刑事上の公訴時効期間の起算点には関係ありません。
横領罪に未遂はない
時効の起算点は犯罪行為が終了した時点ですが、注意すべきなのは横領罪には未遂の処罰規定がない点です。
横領罪は「所有者でなければできないような処分をする意思」が外部に現れた時点で既遂となります。未遂の概念はないため、横領行為に着手した時点で既遂です。
たとえば、預かったDVDを第三者に売ろうとする意思表示をすれば、その時点で既遂となります。第三者が買い受けをする意思を示さなかったとしても、横領罪となる点に変わりはありません。
他の例としては、会社のお金を自分の口座に振り込む行為をした時点で、業務上横領罪が成立します。実際に自分の口座からお金を引き出したか否かは関係ありません。また、後から全額を会社に返したとしても、いったん業務上横領罪が成立している以上、罪を犯した事実は消えません。
横領罪は「所有者でなければできないような処分をする意思」が外部に現れた時点で既遂になり、未遂の概念がないのが特徴です。
時効が過ぎてから横領に気づいた場合
公訴時効期間が過ぎてから横領に気がつく場合もあるでしょう。期間経過後に被害に気がついたとしても、犯人を罪には問えません。
そもそも、被害者が知っていたかどうかは、公訴時効期間のカウントには無関係です。事実として犯行が終わっていれば公訴時効期間のカウントがスタートし、期間が過ぎれば時効が完成し、刑事裁判ができなくなります。
たとえば、長年ゲームソフトを友人に貸していた事実を思い出して確認したところ「10年前に売ったよ」と言われたケースでは、刑事責任は問えません。前述の通り単純横領罪の時効期間は5年であり、すでに経過しています。
公訴時効期間が過ぎてから被害に気がついても、刑事告訴をして罪に問うことはできないのです。
20年以内なら返還請求できる可能性が高い
気がつくのが遅れて加害者に刑罰を科せないとしても、民事上の請求はできる可能性があります。
民法724条には、以下の場合に不法行為による損害賠償請求権が時効により消滅すると定められています。
①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
②不法行為の時から二十年間行使しないとき
まず、被害者が「損害及び加害者」を知っていたときには、3年で時効により請求権が消滅するのがルールです。刑事上の公訴時効期間が過ぎる前に、民事上の請求権がなくなってしまうケースもあります。
もっとも、被害の事実や犯人を知らない状態であれば、3年の消滅時効期間は進行しません。3年を過ぎても民事上の請求が可能です。ただし、横領があった時から20年が経過すると、被害者の認識の有無に関わらず民事上も請求ができなくなってしまいます。
以上より、20年を経過していなければ民事上の返還請求はできます。刑事上の時効期間が過ぎて刑罰を科せなくなっていても、被害の回復を求めましょう。
横領罪の時効に関するよくある質問
横領の時効に関してよくある質問をまとめました。
なぜ横領罪には時効があるの?
公訴時効期間が定められている理由については様々な考え方があり、一般的には以下が挙げられます。
- 時の経過により処罰感情が薄れ、処罰する必要がなくなる
- 時の経過により証拠が散逸し、刑事責任を問うのが難しくなる
- 犯人が一定期間訴追されなかった状態を尊重する
これらは、被害を受けた方からすると理解しがたいかもしれません。
近年、殺人など人を死亡させた罪における時効の撤廃・延長、性犯罪における時効の延長といった、時効を成立させない方向での法改正もなされています。残念ながら横領罪については、従来のままです。
時効がストップするケースはある?
時効期間のカウントがストップする場合もあります。代表的なのは、犯人が国外にいるケースです(刑事訴訟法255条1項)。
犯人が国外にいたとしても、その間の時効のカウントが止まるだけであり、期間がリセットされてゼロになるわけではありません。
横領に気づいたら弁護士に相談!
ここまで、横領罪の時効について、類型ごとの期間、起算点、時効が過ぎてから被害に気がついたときの対処法などについて解説してきました。
横領罪の公訴時効期間は、類型によって3〜7年と、比較的短いです。時間が経ってから被害に気がついた場合には、犯人に罪を問えなくなる可能性があります。早めに対応するのが重要です。刑事上の時効期間が過ぎても、民事上の返還請求はできるケースがあるので、諦めないようにしましょう。
横領の被害に遭われた方は、リード法律事務所までご相談ください。
刑事事件の被害者の方が警察に訴えても、「証拠が足りない」「他の事件で忙しい」「民事不介入」などの理由で取り合ってくれないケースは多いです。当事務所は、被害者の方々から依頼を受け、数多くの告訴を受理させてまいりました。とりわけ、横領事件については、得意にしており、多くの成功実績がございます。当事務所では横領について、証拠収集、告訴状の作成、警察とのやりとり、民事上の請求などを徹底的にサポートいたします。
時効にかからないように、横領被害に気がついたらすぐにお問い合わせください。