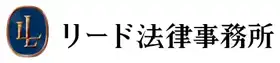業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。実際に科される刑罰の重さは、被害額や示談の有無などによって決まります。
被害額が大きいケースでは、実刑になる可能性が高いです。予想される刑罰が重いと、加害者は被害者と示談をして回避しようとする傾向にあります。
この記事では、業務上横領罪で科される刑罰を状況ごとに紹介し、被害者が返金を受けられるかについて解説しています。業務上横領の被害に遭った方に知ってほしい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
目次
業務上横領罪の刑罰
まずは、業務上横領罪の概要や法定刑についてご説明します。
そもそも業務上横領罪とは?
業務上横領罪は、業務として管理を任された他人の財産を、勝手に自分のものにする犯罪です。典型的なのが、管理権限を与えられた従業員が会社の財産を着服するケースです。
具体的な事例としては以下が挙げられます。
- 経理担当者が、会社の預金を自己名義の口座に移す
- 集金担当者が、取引先から集めたお金を自分のものにする
- 店舗責任者が、売上金を過少に申告して差額を着服する
業務上横領罪では、管理権限を有する従業員が会社からの信頼を裏切っている点がポイントです。権限がない従業員が会社財産を自分のものにしているケースでは、窃盗罪など別の犯罪が成立します。
業務上横領罪の構成要件、窃盗との違いについては、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。
・業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説
・横領と窃盗の違いとは?具体例や被害者がすべきことを弁護士が解説
法定刑は10年以下の懲役
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑とは、法律上科せる刑罰の範囲を意味します。法定刑が「10年以下の懲役」である業務上横領罪においては、有罪判決が下されたときは「1ヵ月以上10年以下」の範囲で刑期が決定されます。
業務上横領罪の法定刑は、単純横領罪(5年以下の懲役)よりも重いです。業務として財産の管理を任されている人が信頼を裏切ると、1回あたりの金額が大きくなりやすいうえに、繰り返されて被害が膨らみやすいため、法定刑が重くされています。
最高で懲役10年というのは、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪などと同じです。これらの犯罪と同様に、業務上横領罪は深刻な被害をもたらす重大犯罪といえます。
罰金刑は規定されていない
業務上横領罪には懲役刑の定めしかなく、罰金刑は規定されていません。有罪となれば必ず懲役です。この点で、罰金も規定されている窃盗罪よりも刑が重い犯罪といえます。
なお、罰金刑がなくても被害者は民事上の損害賠償請求権を有しており、金銭的な被害回復が可能です。(そもそも罰金刑は国にお金を支払う刑罰であり、直接被害者への返金が命じられるわけではありません。)
罰金刑ですむことはなく、懲役刑しか存在しない点で、業務上横領罪は刑罰が重い犯罪といえます。
業務上横領罪で刑罰の重さを左右するポイント
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、実際に言い渡される刑罰は被害額をはじめとする様々な要素により決定されます。被害が軽いケースや示談したケースでは、そもそも起訴されず刑事裁判に至らない場合もあります。
業務上横領罪において、実際の刑罰の重さを左右するポイントを見ていきましょう。
被害額
被害額は特に重要なポイントです。もちろん、被害額が大きければ大きいほど刑罰が重くなります。
被害額が400万円程度以上だと、実刑判決になる可能性が非常に高いです。それよりも少ない金額であっても実刑判決がくだされるケースはありますが、少なければ少ないほど執行猶予つき判決や不起訴処分になりやすいです。
被害弁償や示談の有無
被害弁償や示談をしていると、刑罰が軽くなる方向に作用します。被害を金銭的に補償している、被害者が許しているといった事情は、刑事処分の決定において重視されます。
被害額が少なければ、示談によって不起訴処分になる可能性が高いです。被害額が多く、本来であれば実刑相当のケースでも、示談により執行猶予や不起訴になる場合があります。
前科の有無
加害者に同種前科があると、初犯の場合に比べて刑が重くなりやすいです。
被害額が少なく、初犯であれば執行猶予になるケースでも、前科の存在により実刑判決になる可能性があります。また、執行猶予期間中に業務上横領で有罪判決が下されれば、基本的に執行猶予が取り消され、前回と今回の刑が合わせて科されます。
その他
主な要素は以上に挙げた通りですが、他にも刑の重さを左右する要素があります。
たとえば、犯行態様、動機、社会的制裁などです。社会的制裁とは、刑罰以外に加害者が受けた制裁であり、解雇や実名報道に伴うバッシングなどが挙げられます。
業務上横領罪で実刑・執行猶予・不起訴になるケース
同じ業務上横領罪であっても、個々の事情に応じて実際に下される刑事処分は大きく異なります。実刑・執行猶予・不起訴の違いや該当するケースについて解説します。
実刑・執行猶予・不起訴の違い
業務上横領罪の疑いがある場合、捜査がなされた後に、まずは検察官が犯人を起訴するか否かを判断します。
不起訴処分となれば刑事裁判は行われず、刑罰は科されません。
起訴されると刑事裁判にかけられ、裁判官が有罪か無罪か、有罪のときには量刑を決定します。刑事裁判においては、懲役の年数だけでなく、執行猶予がつくか実刑判決になるかも大きなポイントです。
実刑判決・執行猶予つき判決・不起訴処分の違いをまとめると、以下の表のようになります。
| 実刑 | (全部)執行猶予 | 不起訴 | |
| 前科になるか | なる | なる | ならない |
| 刑務所に入るか | 入る | 入らない | 入らない |
それぞれの処分について、順に詳しく解説します。
実刑だと刑務所に収監される
起訴されて刑事裁判が行われ、有罪と判断されたときは、実刑か執行猶予がつくかが大きな分かれ目です。
実刑判決が下されると、加害者はただちに刑務所に収監されます。懲役の年数分だけ、刑務所で刑務作業に取り組む必要があります。
刑務所に入るのが大変な苦痛であることはご想像いただけるでしょう。加害者の多くは、実刑判決は避けようと考える傾向にあります。
執行猶予でも前科にはなる
有罪であっても、執行猶予がつくケースがあります。(全部)執行猶予つき判決の場合には、ひとまず刑務所には収監されません。猶予期間中に犯罪をせずに過ごせば、実際には懲役刑に服さない結果となります。
たとえば「懲役3年、執行猶予5年」のときは、5年間を何事もなく経過すれば、3年の懲役刑は科されません。もっとも、猶予期間中に犯罪をすれば基本的に執行猶予は取り消され、元の刑期と新たに言い渡された刑期を合わせて刑が執行されます。
執行猶予がつく可能性があるのは、懲役が3年以下のケースに限られます。3年を超える懲役刑は、必ず実刑です。懲役3年以下でも、必ず執行猶予がつくわけではなく、実刑となるケースもあります。
執行猶予がつくと刑務所に収監されませんが、有罪判決である以上、前科にはなります。したがって、前科に伴う社会的・経済的な不利益は避けられません。
不起訴になると前科がつかない
不起訴処分になると、そもそも刑事裁判か開かれず有罪判決は出ないため、前科にもなりません。
加害者の立場からすると、まずは最もダメージが少ない不起訴処分の獲得が目標となります。
実刑になるケース
業務上横領罪で実刑判決が下されるのは、被害額が大きいケースです。
とりわけ被害額が400万円程度を超えると、初犯であっても示談しない限り実刑判決となる可能性が非常に高いです。加害者が被害弁償して示談すれば実刑を免れる道が開かれますが、あまりに被害額が大きい場合には示談しても実刑です。
被害額が400万円程度に至らなくとも、百万円単位の被害があれば実刑となる可能性はあります。また、被害額が少なくても加害者に同種前科があると実刑になり得ます。執行猶予期間中の犯行であった場合は、基本的に執行猶予が取り消されたうえで実刑になります。
執行猶予になるケース
業務上横領罪で執行猶予がつきやすいのは、初犯で被害額が大きくないケースです。
また、被害額が400万円程度以上で起訴されれば通常は実刑となるものの、起訴後に示談した結果、執行猶予がつくケースもあります。
不起訴になるケース
不起訴になるケースとしては、まず起訴前に示談したケースが挙げられます。示談によって被害者が加害者を許していれば、検察官が被害者の意思を尊重して不起訴処分となりやすいです。
また、被害がごく軽微な場合には、示談していなくても処罰する必要性が低いと考えられ、不起訴となります。
業務上横領罪で想定される刑罰の重さが返金の可否に与える影響
実は、想定される刑罰の重さが、被害額が返金されるかを大きく左右します。重い刑罰が想定される際には、刑罰を回避するために加害者が示談・返金に積極的になりやすいです。
ここでは、想定される刑罰と返金の可否の関係を解説します。返金の可否については、以下の記事も合わせてご参照ください。
参考記事:横領されたお金は返ってくる?返済されやすいケースと方法を弁護士が解説
実刑になりそうだと回避するために返金可能性が高まる
実刑判決が下されて刑務所に収監されると、家族に会えず仕事もできないため、社会的・経済的に大きなダメージを受けます。加害者の立場からすると何としてでも避けたい事態です。
実刑判決が予想されるケースでは、刑務所への収監を避けるには、事実上被害額を返金して被害者と示談するほかありません。そのため、加害者が返金する姿勢を示す可能性が高まります。
もちろん、返金するにはお金が必要です。しかし、加害者本人にお金がなくても、親族などから借金をしてまで用意するケースもあります。
被害額が大きいケースでは、民事訴訟で勝訴しても、強制執行の対象にできる財産が十分になく、結局回収できない可能性が高いです。しかし、重い刑罰を科されるリスクがあると、加害者は何としてでも返金しようと考える傾向にあります。そのため、被害者が刑事告訴によって事件を捜査機関に申告し、刑罰権の行使を現実的なものとするのが効果的です。
横領で刑事告訴をするメリット・デメリットについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
執行猶予では前科による不利益の大きさが重要
執行猶予が予想されるケースでは、前科による不利益の大きさが返金の可否を左右します。
執行猶予がついても、前科になる点は変わりません。前科がつくと、社会的・経済的に大きな不利益が生じます。たとえば、配偶者に離婚される、職場を解雇されたうえに再就職も難しくなるといった不利益です。
加害者にとって前科に伴う不利益が大きい場合には、たとえ実刑にならないにしても、返金して示談に応じてもらい、不起訴処分を獲得するモチベーションが生じます。具体的には、既婚者で子どもがいる、正社員であるなど、「犯罪者になると失うものが大きい」属性の人は、返金による示談を目指しやすいです。とりわけ収入が多く、お金を用意できる加害者であればなおさらです。
反対に、独身で非正規雇用であるなど、前科がついても比較的ダメージが小さい加害者については、返金に応じてもらえる可能性が低くなります。現実的に考えると、収入が少ないとお金を用意するのが困難でもあります。
執行猶予がつくと想定されるケースでは、加害者の属性上、前科に伴う不利益が大きいかがポイントです。
不起訴が予想されるとプレッシャーにはなりづらい
被害額が少ないなど、不起訴処分が想定される場合には、加害者が返金に応じる動機が高まりづらいといえます。刑事告訴をしても「どうせ不起訴になるなら返金は不要」と考えられてしまいやすいです。
刑罰によるプレッシャーが期待できないときは、被害額が大きくなるまで待つという方法もあります。業務上横領は繰り返されやすいため、時間が経つと被害額が膨らみ、想定される刑事処分が重くなる可能性があります。
とはいえ、状況判断は難しいです。被害者側の弁護に精通した弁護士に相談し、対応を検討するのがよいでしょう。横領の被害者側に強い弁護士については、以下の記事をお読みください。
参考記事:横領の被害者側に強い弁護士とは?依頼のメリットや選び方を解説
業務上横領の被害に遭ったら弁護士にご相談ください
ここまで、業務上横領の刑罰や返金の可否に与える影響について、被害者の視点から解説してきました。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、実際に科される刑罰は被害額などによって決まります。被害額が大きく重い処罰が予想されるケースでは、被害を取り返すために刑事告訴が特に有効です。ただし、刑事告訴は簡単には受理してもらえないため、弁護士への相談をオススメします。
業務上横領の被害を受けた方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所は犯罪被害者の弁護に力をいれており、横領でも告訴を受理させてきた実績がございます。証拠収集から告訴状の作成、警察とのやりとり、加害者との交渉まで徹底的にサポートいたします。
「業務上横領をした従業員に刑罰を科したい」「返金してもらいたい」などとお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所に横領の刑事告訴を依頼いただいた際の流れはこちら