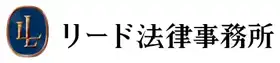「従業員による横領が判明した」とお悩みでしょうか?
社内で横領があったときには、解雇などの懲戒処分だけでなく、刑事告訴も検討する必要があります。
告訴すれば刑事処分を科せる反面、必ず満足のいく結果になるとは限りません。十分に調査・検討したうえで、対処方針を決めるようにしましょう。
この記事では、業務上横領した従業員を刑事告訴するメリット・デメリットや告訴のポイントなどを解説しています。社内で発生した業務上横領について刑事告訴すべきかお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
従業員による業務上横領が発覚したら、どうすべき?
社内での着服行為が発覚した場合には、どうすべきなのでしょうか?
まずは、成立する犯罪や初動対応など、基本的な知識を解説します。
横領罪で刑事告訴できる
従業員が会社の財産を着服すると、業務上横領罪が成立する可能性があります。
横領罪とは、他人から管理を任された財産を自分のものにする犯罪です。業務上管理を任された金品を自分のものにすると、業務上横領罪が成立し、単なる横領罪よりも罪が重くなります。
業務上横領罪となる典型例は、会社の経理担当が、管理を任されている会社の金銭を着服するケースです。着服以外にも、売却・隠匿など、本来所有者しかできないはずの行為が横領に該当します。
業務上横領罪が成立するときには、会社は被害者として刑事告訴ができます。
刑事告訴とは、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して処罰を求めることです。刑罰は告訴がなくても科せるものの、横領は被害者の申告がなければ発覚しづらいため、業務上横領罪では告訴が特に有効な手段です。
会社の財産の管理を任され占有している状態で、従業員が自分の懐に入れると業務上横領となります。権限がない者が会社の金品を自分のものにしたときには、窃盗に該当します。
たとえば、他部署の従業員が、経理担当が管理する金銭を自分のものにしても、権限がないため業務上横領にはなりません。このとき成立するのは窃盗罪です。
権限があいまいで横領か窃盗かの判断が難しいケースもあるため、事前に弁護士に確認するとよいでしょう。
刑事告訴する前に、まずは事実確認をすべき
業務上横領の疑いがあるときには、告訴する前に入念に事実確認をしてください。
証拠が十分にないのに業務上横領と断定して手続きを進めると、犯人とされた従業員から反発を受けるリスクが高いです。解雇が不当だとして賃金の支払いを求められたり、名誉毀損だとして損害賠償請求をされたりする可能性があります。
そもそも、十分な証拠がなければ刑事告訴や民事上の返還請求ができません。事実確認は必須です。
事実確認の方法としては、他の従業員からの聞き取りや、客観的な記録の確認が挙げられます。他の従業員と共謀して横領している可能性もあるため、聞き取りの際には注意が必要です。証拠隠滅を防ぐために、早めに決定的な証拠をつかむようにしてください。いきなり本人に事情を確認するのは避けましょう。
▼業務上横領が起きた時の会社の対応に関してはこちらをご覧ください
業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
横領罪で刑事告訴できる事例
業務上占有する他人の財産を自分のものにすると、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪が成立し刑事告訴できるケースとしては、以下が挙げられます。
経理担当者が会社の預金を自分の口座に振り込んで横領した事例
会社の金銭を扱う経理担当者は、誘惑に駆られて横領を犯しやすいです。
たとえば、会社の預金から、自己名義や自分で設立した法人名義の口座に振り込みをする事例があります。送金が多数あると紛れてしまい、気づかれないケースが考えられます。
特に経理担当者が1名で他の従業員からのチェックがないと、繰り返し犯行に及び、被害が大きくなる可能性が高いです。
経理担当者が第三者と共謀し、架空の請求書を使って横領した事例
経理担当者が取引先などの第三者と共謀し、架空の請求書を発行させるケースもあります。実態のない架空の取引をでっち上げ、会社のお金を着服するのです。
一応請求書は作成されるため、理由なく送金する場合に比べて巧妙な手口です。複数の経理担当者がいたとしても、手の込んだ請求書であれば気づかれない可能性があります。取引先に調査しても、共犯者であるため正直に答えないケースも多いでしょう。
集金した売掛金を担当者が持ち逃げした事例
集金を担当する従業員が、顧客から回収したお金を持ち逃げする事例もあります。管理報告体制が十分でなかったり、本人が「集金できなかった」とウソをついたりすると、持ち逃げが可能になります。
顧客から受け取った金銭は、本来会社の財産です。集金担当者は回収した金銭を一時的に保管する権限がありますが、実際には会社のものである以上、持ち逃げすれば横領となります。
持ち逃げが疑われるときには、顧客に支払いの証拠を確認するなどして、被害の実態を確かめてください。
店長・支店長が売上額を過少申告し、差額を着服した事例
店長・支店長といった現場レベルの責任者が、売り上げを過少報告するケースも考えられます。実際の売上額との差額を、自分の懐に入れてしまうのです。
各店舗の責任者に対しては、普段は監視の目が行き届いていない可能性があります。発覚したときには被害が膨らんでいる事例も少なくありません。売り上げの記録を確認し、不審な点がないかをチェックする必要があります。
横領罪で従業員を刑事告訴するメリットとは?
業務上横領罪が成立する場合には、刑事告訴を検討しましょう。
刑事告訴をすると、以下のメリットがあります。
刑事責任を追求できる
そもそも刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求めることです。告訴すれば、刑事責任を追及する道が開かれます。
業務上横領罪は、起訴して刑事裁判にするために告訴が不可欠な「親告罪」という類型の犯罪には該当しません。しかし、組織内部で行われるため、性質上被害者が申告しないと捜査機関に明らかにならない犯罪といえます。刑事処分を科したいのであれば、被害の申告が必要です。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。比較的重い部類の犯罪といえ、被害金額が大きければ実刑判決がくだされます。
社内で発生した横領について刑事裁判で処罰を科して欲しいと考えているのであれば、告訴を検討しましょう。
被害額を回収できる可能性が増す
告訴によって、被害の弁償を受けられる可能性が高まります。
たしかに、告訴した結果として犯人が処罰されたとしても、着服された金品を返してもらえるわけではありません。
とはいえ、犯人が重い刑事処分を回避したいと考えれば、告訴をきっかけに返還するモチベーションが生じます。被害弁償によって不起訴処分になる、あるいは起訴されて裁判になっても刑が軽くなる可能性が高いためです。
したがって、被害を少しでも回復したいときにも、刑事告訴は有効な手段となります。
ただし会社から見れば、重い刑事処分を求める場合は被害弁償がマイナスに作用します。犯人からの申し出を受け入れるかは、慎重に検討してください。
再発防止につながる
刑事告訴は、社内での再発防止にもつながります。
業務上横領に対して刑事告訴という重大な手続きをとれば、「不正行為は許さない」との強いメッセージになります。本人のみならず他の従業員に対しても「会社は本気だ」「今後も着服は決してしてはならない」と思わせることが可能です。
告訴せず内密にしておけば、たしかに世間に知られずに済むかもしれません。しかし、「着服しても処分が甘かった」「さほど問題ではない」との印象が社内に広まるリスクがあります。本人あるいは他の従業員が、再び犯行に及ぶ可能性も否定できません。
刑事告訴により業務上横領への厳しい姿勢を示せば、今後の被害を防ぐ効果も期待できます。
横領罪で従業員を刑事告訴するデメリットとは?
告訴には上記のメリットがありますが、万能ではありません。以下の点には注意してください。
刑事告訴だけでは、被害回復できない
刑事告訴をしたからといって、被害の回復に直結するわけではありません。
告訴により求められるのは「10年以下の懲役」という刑事処分だけです。刑事訴訟になったからといって、返金される保証はありません。被害を回復するには、示談によって自発的に返還してもらうか、民事訴訟を起こして勝訴判決を得たうえで回収する必要があります。
前述の通り、たしかに告訴により犯人側に示談をするモチベーションが生じる側面はあります。ただし、着服した金品を示談のために会社に返還するかは、最終的に加害者次第です。既に使い切っている可能性も高いです。
ときどき「告訴をすれば被害を弁償してもらえる」と思っている方もいます。しかし、刑事告訴と民事的な弁償は別問題です。返してもらえない可能性も頭に入れておいてください。
被害額として認められる額が下がる可能性がある
告訴によって、被害額として認定される金額が下がるケースもあります。
刑事上は、確実な証拠がある部分についてしか、被害として認めてくれません。警察や検察は、(一部)無罪判決が出るのを避けるために、被害の一部しか告訴を受理してくれない可能性が高いです。
現実には、「業務上横領された」と会社が考えている金品すべてについて明確な証拠が残っているケースは、むしろ珍しいでしょう。したがって、告訴により被害を申告すると、被害額として認められる金額が思ったより少なくなります。
被害額の減少に伴って、犯人から弁償を受けられる金額も減ってしまいます。告訴を検討する際には、弁償してもらえる範囲が狭くなるリスクも考慮して判断してください。
解決するまでに時間がかかる
告訴したときには、最終的な解決まで時間がかかる可能性があります。
まず、証拠を集めて告訴状を作成し、警察に受理してもらうまでに一定の期間を要します。証拠不足などの理由で簡単に受理してもらえないためです。
受理されたとしても、捜査がスムーズに進まない場合があります。事件が複雑である、捜査すべき範囲が広いなど、起訴まで時間がかかるケースが想定されます。
起訴されたとしても、すぐに裁判で判決が出るとは限りません。犯人が事実を争うなどすれば、長期化する可能性があります。
会社内部で処理すれば早期の解決もできますが、刑事処分になると簡単にはいきません。告訴をする場合には長期戦も覚悟してください。
既に返金された場合でも横領罪で刑事告訴できる?
告訴する前に、従業員から自主的に返金を受けるケースもあります。既に返金を受けた場合にも、業務上横領罪で刑事告訴できるのでしょうか?
原則、横領罪で刑事告訴することは可能
既に返金されていても、原則として告訴は可能です。
業務上横領罪は、管理を任されていた財産を自分のものにする意思が行動に現れた時点で成立します。いったん成立すれば、後から何をしても犯罪の成否そのものには無関係です。犯人が罪を認めて返金したとしても、業務上横領罪が成立している点に変わりはありません。
したがって、既に返金を受けたケースでも刑事告訴はできます。
示談の条件で、告訴しないとした場合は難しい
もっとも、すでに示談していて、条件の中で「刑事告訴はしない」と合意していれば告訴は難しいです。
有効に成立した示談の内容は、当事者を拘束します。返金を受けたうえで「被害届の提出や刑事告訴はしない」と定めて示談していれば、従わなければなりません。合意に反して告訴をすれば、損害賠償請求をされるおそれがあります。
返金の約束をして示談をしたものの、実際には返金がなされないケースも想定されます。「相手が約束を破ったのだから告訴してもいいはずだ」と考えるかもしれません。しかし、警察からは「民事上の問題だ」として取り合ってもらえない可能性があります。後払いのときには「全額返金があったら告訴しない」との内容にするべきです。
いずれにせよ、「刑事告訴はしない」との示談をしたときには、合意内容を守らなければなりません。
告訴を一度取り消した場合は?
いったん告訴を取り下げたものの、「やはり処罰して欲しい」と再度告訴を考える場合もあるでしょう。
法律上「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない」とされています(刑事訴訟法237条2項)。もっとも、この条文は起訴のために告訴が不可欠な「親告罪」のみに適用されるとの考えが一般的です。業務上横領罪は非親告罪なので、再度の告訴は禁じられてはいません。
ただし、返金を受けて「告訴は取り下げる」との内容で示談をしていれば、合意内容に拘束されます。通常であれば再告訴は受理してもらえないでしょう。
業務上横領罪については、告訴を一度取り消しても再告訴が可能です。とはいえ、告訴を取り下げる際には慎重に検討してください。
横領罪で従業員を刑事告訴するときのポイント
横領が発覚したら、すぐにでも告訴したいと考えるかもしれません。しかし、焦りは禁物です。
業務上横領罪で従業員を刑事告訴する際には、以下のポイントに気をつけて慎重に進めてください。
事前調査をし、証拠を確保する
犯行があったかについて事前に十分な調査をして、証拠を確保するようにしてください。
そもそも十分な証拠がなければ、告訴を受理してもらえません。警察・検察は、確実に有罪になると考えられる事件だけを捜査対象にする傾向にあるためです。
また、証拠がないのに犯人だと決めつけて告訴や懲戒処分の手続きを進めると、対象となった従業員から訴訟を起こされるリスクもあります。
調査としては、他の従業員や取引先への聞き取り、取引などに関する客観的な記録の収集が考えられます。ただし、犯人や協力者に調査を悟られると証拠を隠滅されるおそれがあるため、慎重に進めてください。
早めの調査と証拠確保は大きなポイントになります。
本人から事情聴取し、自白させるのも有効
証拠が集まったら、本人から事情聴取をします。
聞き取った内容は必ず記録をとり、横領の事実に間違いがないことを本人に書面で確認させてください。質問する人とメモをとる人を別にするとよいでしょう。
もし否定されたとしても、言い分を記録しておけば、矛盾を追及しやすくなります。動かぬ証拠を突きつければ認めるケースもあります。
本人の自白があれば、後の手続きがスムーズです。とはいえ、あまりに強引に言わせようとすると「無理やり自白させられた」と主張されるリスクがあります。あくまでも言い分を聞く姿勢を持ってください。
また、刑事裁判においては自白だけでは有罪にできません。自白するにせよ、他の証拠で証明できるのが前提になります。
裏付けが取れた横領の件で告訴する
告訴をするのは、証拠で裏付けがとれた部分についてのみにするとスムーズです。
捜査機関は証拠がなかったり弱かったりすると、告訴を受理してくれません。事実を証明できず、無罪になる可能性がある事件を扱いたくはないためです。証拠が十分ある部分に絞れば、告訴が受理されやすくなります。
被害額がより大きいと考えているときには、範囲を限定するのはためらわれるかもしれません。しかし、刑事罰を求めるのであれば確実な証拠が必要です。法律上どこまで認めてもらえるか判断できないときには、弁護士に相談しましょう。
まとめ
ここまで、横領の刑事告訴について、メリット・デメリット、注意すべきポイントなどを解説してきました。
告訴すれば、横領について刑事罰を科す道が開かれます。十分な証拠を集めたうえで、告訴するか否かを検討しましょう。
従業員がした横領について刑事告訴をすべきかお悩みの方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所では、被害者の方々から依頼を受け、数多くの告訴を受理させてまいりました。証拠収集や警察とのやりとりなど、告訴に関して徹底的にサポートいたします。
従業員の横領を告訴すべきか悩んでいる、警察に取り合ってもらえず困っているといった方は、まずはお気軽にお問い合わせください。