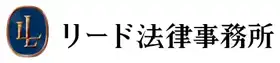会社内で発生しやすい不正のひとつが横領です。横領している人の特徴としては、お金に困っている、犯行ができる立場にあるといった点が挙げられます。
横領を未然に防ぐには、外部の目を入れる、社内でダブルチェックするといった対策が考えられます。もし横領の疑いが生じたら、すぐに証拠を集めたうえで、懲戒解雇、民事上の返還請求、刑事告訴といった措置を検討しなければなりません。
この記事では、横領しやすい人の特徴や会社が注意すべきポイント、横領している人が見つかったときの対処法などを解説しています。社内での横領に対応したいと考えている会社関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
横領罪に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:【被害者向け】横領罪とは?類型と量刑、構成要件について解説
目次
横領してる人の特徴
横領に至るには、お金に困っているなど相応の理由があります。それだけでなく、犯行ができる立場になければ、実際に横領はできません。また、不正に手を染めやすい性格の持ち主である場合が多いです。
以下で、横領をしている人の特徴を詳しくご説明します。
横領する理由がある
横領という犯罪行為に及ぶには、それなりの理由があります。
動機として思いつきやすいのは、お金に困っていることでしょう。他に、会社への不満が不正行為に至る要因になるケースも存在します。
お金が必要
お金に困っていると、横領する動機になります。会社で扱っている金品の量は個人とはレベルが異なるため、お金を必要とする従業員にとっては魅力的に移るでしょう。
金銭的に困る理由は様々です。
- ギャンブル依存症である
- 浪費癖がある
- 借金を抱えている
- 見栄っ張りで高価な物を購入している
- 投資に失敗した
こうした事実や噂がある従業員には注意しなければなりません。
会社への不満を抱えている
深刻な金銭的問題を抱えていなくても、会社への不満が不正の動機になる場合があります。たとえば、上司が気に入らない、ノルマが過大である、報酬が少ないといった不満です。
「そんな理由で犯罪をするのか」とお感じになるかもしれません。しかし、会社に大きな不満を抱えている従業員は、報復のために手段を選ばない場合があります。「会社の評判を下げてやろう」とまで考える加害者も存在します。
したがって、会社に不満を持っている従業員がいないかにも気をつけなければなりません。
犯行ができる立場にある
いくら動機があっても、実際に横領が可能なポジションにいない限り、犯行には至りません。社内で横領ができる立場としては、以下が挙げられます。
責任が重い
社内で責任が重い立場にある人は、横領をしやすいといえます。
そもそも、業務上横領罪は、管理権限を任されている人が、会社の財産を自分の物にしたときに成立する犯罪です。したがって、会社の金品について一定の権限・責任がある人が業務上横領罪の加害者になり得ます。もちろん権限がない人が会社の財産を奪うのも大きな問題ですが、多くの場合で法律上は横領ではなく窃盗に該当します。
法律論は別にしても、現実問題として、会社において上位の役職に就いている人は、他の人から監視・監督されずに行動しやすいでしょう。そのため、気がつかれずに横領が実行できてしまいます。
中には、社長や役員が横領に及ぶケースもあります。たとえ社内で信頼されていて責任が重い立場にある人であっても、権限が強いがゆえに不正に手を染めてしまう場合があるのです。
業務上横領罪の基礎知識や横領と窃盗の違いについては、以下の記事をお読みください。
(参考記事)
・業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説
・横領と窃盗の違いとは?具体例や被害者がすべきことを弁護士が解説
お金を扱う
社内でお金を扱う立場にある人は、横領を犯しやすいといえます。横領の対象になるのは多くのケースで金銭であるためです。
特に横領に及びやすいのは経理担当者です。社内のお金の流れに詳しい経理担当者は、バレずに着服する方法もわかっています。日常的に会社のお金を扱っているがゆえに、つい出来心で犯行を始めてしまい、次第にエスカレートするケースも多いです。高額の被害も発生しやすいといえます。
他には、顧客・取引先からの集金担当者も横領しやすいです。たとえば、受け取った現金をそのまま懐に入れ、会社には未回収であると虚偽の報告をする事例があります。仮に少額であっても、犯罪である点に変わりはありません。少額の横領への対処法については、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領罪は少額でも成立する?被害者ができることを解説
物品を扱う
横領の対象は金銭だけではありません。会社の物品を扱う立場にある従業員が横領に及ぶケースもあります。
たとえば、会社のオフィス用品などの備品を管理している人や、倉庫にある商品在庫を管理する責任者などが横領に及ぶ可能性があります。数量を他の社員が把握していない状態では、物品の横領が発生しやすいです。
横領しやすい性格である
横領する理由があって立場上可能であるとしても、簡単には犯罪行為に及びません。横領しやすい性格であると、最終的に犯行に至る可能性が高くなります。
ルールを守らない・非を認めない
横領しやすい人の性格の特徴としては、ルールを守らない、非を認めないといった点が挙げられます。
ルールを守る意識が低い人は、一般的な人と比べて犯罪を実行するハードルが低いです。また、不正が判明して追及されても、「会社の管理がずさんなのが悪い」「自分を評価しなかった結果だ」などと責任転嫁する場合があります。
普段からルールを守らず、自分の行動を正当化する傾向にある従業員には注意した方がよいでしょう。
バレないように行動する賢さがある
ルールを守らない・非を認めない社員は、もとより疑いの目を向けられやすいでしょう。反対に、意外な人が横領に手を染めるケースも少なくありません。
思いもよらぬ人が不正に及んでいるときは、横領をバレないように実行する注意深さや賢さを持っている場合が多いです。そうした人は責任ある立場を任されやすく、経営者や他の従業員が信頼しているのを利用して犯行に及びます。
「あの人は大丈夫」と信頼し過ぎると、思わぬ落とし穴があるので気をつけてください。
業務上横領を発生させないためのポイント
社内で横領を発生させないためには、以下のポイントに注意しましょう。
金品の管理を厳格にする
金品の管理が不十分だと横領が生じやすいです。未然に防ぐために、金銭や備品・在庫の管理を厳格にしましょう。
経営者や上位の役職者が把握しやすい状態にするだけでなく、外部の専門家の目を入れるのも有効です。税理士や公認会計士が定期的にチェックしていれば、不正もしづらくなるはずです。
ひとりに任せない
金銭等の管理をひとりの従業員に任せないようにしてください。
たとえば、中小企業では経理担当者がひとりで、他の従業員はお金の流れを把握していないケースがあるでしょう。ひとりに任せきりにせずに、ダブルチェックをすれば、不正が生じるリスクを大幅に下げられます。
また、内部通報窓口を設置して、他の従業員が不正を訴えやすい環境を整えるのも重要です。従業員同士で不正がないかチェックできる体制にしましょう。
現金の取り扱いを減らす
現金は不正の温床です。授受の記録が残りづらく、口裏合わせも可能であるため、横領が生じる原因となります。
振り込みなど記録が残る方法で金銭をやりとりすれば、不正が発生した際の証拠になるとともに、抑止効果もあります。やむを得ず現金を利用する場合でも、管理を厳格にしてください。
日頃から教育・コミュニケーションを心がける
日頃から従業員への働きかけをして、不正の芽を事前に摘んでおくのも重要です。
たとえば、不正行為に関する社内研修をする、面談を通じて不満を抱えていないか確認する、普段のコミュニケーションの中で変わった様子がないかチェックするといったやり方があります。
不正を防ぐには、日常的な取り組み・心がけを怠らないようにしましょう。
横領してる人が見つかったときの対処法
いくら対策をしていても、横領が発生してしまうケースはあります。ここでは、見つかったときの対処法を簡単に解説します。より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
証拠を集める
横領の疑いが生じたら、すぐに証拠を集めてください。
懲戒処分、返還請求、刑事告訴のうちいかなる方法をとるにせよ、証拠は不可欠です。時間が経つと自然に消えたり、犯人が隠滅を図ったりするおそれがあるため、早めに収集しましょう。客観的な証拠が重要です。
証拠はケースに応じて異なりますが、たとえば以下が考えられます。
- 防犯カメラ映像
- 契約書・領収書などの書面
- 預金通帳など金銭の動きがわかる記録
- メールの文面
証拠を十分に揃えてから、最後に加害者に事情聴取をしましょう。証拠が不十分な状態でいきなり加害者に話を聞くと、否定され証拠隠滅に動かれてしまうリスクが高いです。
業務上横領の証拠について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説
とるべき手段を検討する
証拠が揃ったら、とるべき手段を検討します。
主に考えられる手段は、社内での懲戒処分、民事上の返還請求、刑事告訴です。一部だけ行っても、すべて実行しても構いません。順に解説します。
懲戒処分
まず考えられるのが社内での懲戒処分です。本人だけでなく、他の従業員に対し会社として不正を許さない姿勢を示すために、厳しい処分が必要になります。
懲戒処分の種類は様々ありますが、横領という犯罪行為に及んでいる以上、懲戒解雇が相当であるケースが大半です。
ただし、不当に解雇すれば、無効と判断され多額の金銭支払いを強いられるリスクがあります。就業規則に規定があることを確認したうえで、本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏んでください。
民事上の返還請求
民事上の返還請求も考えられます。交渉や訴訟を通じて被害額を返還してもらえば、金銭的には被害を回復できます。
ただし、金額が大きいと全額の回収は困難です。お金に困って横領に及んでいるのであれば、加害者の財産は乏しいと考えられ、たとえ勝訴判決を得ても強制執行による回収は難しくなります。横領により得た金銭も使い切っているでしょう。
法的に請求が可能であっても、実際に取り返すのは困難といえます。横領されたお金が返ってくるかについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:横領されたお金は返ってくる?返済されやすいケースと方法を弁護士が解説
刑事告訴
業務上横領罪で刑事告訴する方法もあります。刑事告訴とは、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に伝え、犯人の処罰を求める意思を示す行為です。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。被害額が400万円程度以上であるなど、刑事裁判で実刑判決が下され、直ちに犯人が刑務所に収監されるケースもあります。横領は会社が申告しないと警察・検察に判明しづらいため、刑事罰を求めるのであれば告訴は有効な手段です。
さらに、告訴により刑罰が現実的なものになると、加害者は処罰をおそれ、返金に積極的になるケースが存在します。実刑が予想される場合はもちろん、執行猶予で済むとしても、前科がつけば社会的・経済的に大きな不利益が生じます。不利益を避けるために、家族などからお金を集めて弁償し、示談しようとする可能性もあります。
刑事告訴は本来刑罰を求めるために行うものです。しかし、結果として返金につながるケースもあります。横領で刑事告訴するメリットについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
横領している社員がいたら弁護士にご相談ください
ここまで、横領している人の特徴や、未然に防ぐ方法、発生した際の対処法を解説してきました。
お金に困っている、犯行ができる立場にあるなど、様々な条件が重なると横領が発生します。まずは社内体制の整備により、横領が発生しにくい会社にするのが重要です。万が一発生した際には、迅速に証拠を集め、加害者への措置を検討しなければなりません。
横領している社員がいる会社の関係者の方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所は、犯罪被害者弁護に力を入れており、横領でも数多くの告訴を受理させて参りました。証拠収集から告訴状の作成、警察への提出、加害者との交渉に至るまで、徹底的にサポートいたします。
横領被害にお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。