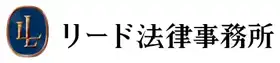業務上横領の被害に遭ってから時間が経過すると、時効にかかって加害者に法的責任を追及できなくなるおそれがあります。
業務上横領罪の公訴時効期間は7年です。犯行から7年が経過すると、刑罰は科せません。
民事上の請求にも時効があり、「損害及び加害者を知った時から3年」あるいは「行為の時から20年」が経過すると、損害賠償を求められなくなってしまいます。
時効にかからないにしても、時の経過とともに証拠は失われるため、早めに刑事告訴や民事訴訟を行わなければなりません。
この記事では、業務上横領の刑事・民事上の時効期間や起算点、被害者がすべき行動などについて解説しています。被害に遭われた方は、ぜひ最後までお読みください。
単純横領罪も含め、横領罪全般の時効について知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
参考記事:横領罪の時効は?いつから数えるのか(起算点)時効が過ぎたらどうすべきかを解説
目次
従業員が横領・着服すると業務上横領罪が成立する
そもそも業務上横領罪とは、業務として管理を任された他人の財産を自分のものにする犯罪です。従業員が会社の財産を着服するケースが典型例です。
具体的には、以下の例が挙げられます。
- 経理担当の社員が、会社の口座から自己名義の口座に振り込みをする
- 集金担当の従業員が、取引先から回収したお金を持ち逃げする
- 店舗の責任者が、売上げを過少に申告して差額を懐に入れる
法定刑は「10年以下の懲役」です。通常の横領罪は「5年以下の懲役」ですが、仕事として預かっている財産の規模は大きくなりやすいため、より刑罰が重くなっています。従業員が巨額の財産を着服すれば、実刑判決となり刑務所に収監されるケースもあります。
業務上横領罪の成立要件や量刑について詳しくは、以下の記事を参照してください。
参考記事:業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説
業務上横領では刑事と民事の時効がある
業務上横領を犯した加害者に対しては、法的責任を追及できます。
方法は大きく分けて2つです。
- 刑事告訴や被害届の提出を通じて刑罰を求める
- 交渉や民事訴訟によって損害賠償を求める
いずれの方法をとるにしても、時効による期間制限があります。時効期間を過ぎてしまうと法的責任を追及できなくなってしまうため、早めに動かなければなりません。
以下で刑事と民事のそれぞれの時効について、意味を簡単に解説します。
刑事の公訴時効とは?
刑事上の時効は「公訴時効」と呼ばれます。法律で定められた公訴時効期間を経過すると、起訴して刑事裁判で刑罰を科すことができません。
公訴時効が定められている理由としては、一般的に以下が挙げられます。
- 時の経過とともに処罰感情が薄れる
- 時の経過により証拠が散逸し、間違いのない裁判をするのが難しくなる
- 犯人が一定期間訴追されなかった状態を尊重する
公訴時効期間の長さは、主に刑罰の重さによって犯罪ごとに決まっています。
時間が経ったからといって犯人が刑罰を免れるのは、被害者からすると理解できないかもしれません。近年は時効期間を延長する法改正もなされ、殺人など一部の重大犯罪では公訴時効が撤廃されています。
民事の消滅時効とは?
民事においては「消滅時効」という制度が存在します。消滅時効期間が経過すると、民事上の損害賠償請求などはできません。
民事上の時効が存在する理由としては、以下が挙げられます。
- 長期間続いた状態を尊重し、法律関係を安定させる
- 時が経過すると事実の立証が困難になる
- 長期間にわたって権利を放置した人は法的保護に値しない
特に消滅時効によくあてはまるのは、1番下の点です。
犯罪被害者は加害者に対して、損害賠償請求権など民事上の請求権を持っています。しかし、行使しないで放置していると、消滅時効にかかって権利がなくなってしまいます。
業務上横領の刑事の時効
業務上横領にも、刑事と民事でそれぞれ時効期間が定められています。まずは、刑事の公訴時効について解説します。
業務上横領罪の公訴時効期間は7年
業務上横領罪の公訴時効期間は7年です。
公訴時効期間は主に犯罪の刑罰の重さによって決まっています。最高で懲役10年の業務上横領罪では、時効期間は7年とされています(刑事訴訟法250条2項4号)。通常の横領罪では5年であるのと比べると、法定刑が重い分、時効期間が長いです。
とはいえ、犯行から7年が経過すると時効が完成し、罪に問えなくなってしまいます。犯行に気がつくのが遅くても、時効は犯行から7年である点に変わりはありません。
時効の起算点
時効には起算点があります。起算点とは、時効のカウントが始まる時点です。起算点からカウントを始め、所定の期間が過ぎると時効が完成します。
以下で公訴時効の起算点について詳しく解説します。
横領行為が終わった時
一般的に公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」です(刑事訴訟法253条1項)。業務上横領の場合には、横領行為が終わった時点から時効のカウントが始まります。
たとえば、以下の時点が起算点になります。
- 会社の口座から自己名義の口座に振り込んだ時
- 集金したお金を自分の財布に入れた時
業務上横領罪には未遂がなく、「所有者でなければできないような処分をする意思」が外部に現れた時点で既遂です。自己名義の口座から預金を引き出した時点ではなく、口座に振り込んだ時点で業務上横領罪が成立し、時効のカウントがスタートします。
複数回の横領があったら?
横領行為が1回であれば、時効の起算点は比較的わかりやすいでしょう。
少し複雑なのが複数回の横領があったケースです。横領は繰り返されやすく、複数回あるのが一般的といえます。
複数回の横領があっても別々に罪が成立し、時効期間も別々に進行するのが基本です。ただし、複数回横領したときには「包括一罪」としてまとめて扱われ、最後の行為が時効の起算点とされるケースがあります。
包括一罪とされ得るのは、被害法益が同じで、同一または継続した意思のもとで似たような横領行為が繰り返された場合です。たとえば、3日に分けて、会社の口座から自己名義の口座に100万円ずつ振り込むケースが挙げられます。
複数回の横領行為が別々に扱われるか、まとめて1つの罪とされるかに明確な基準はありません。現実には判断が微妙なケースも多いです。
共犯者がいたら?
複数人で協力して横領に及んでいるケースもあります。共犯の場合には、最終の行為が終わった時点から、全員について時効期間のカウントがスタートします(刑事訴訟法253条2項)。
時効がストップするケース
時効期間のカウントがストップする場合もあります。典型例が、犯人が国外に逃亡したケースです(刑事訴訟法255条1項)。
ただし、期間がリセットされてゼロになるわけではありません。国外にいる間はカウントが止まり、帰国すると再開されます。
業務上横領の民事の時効
横領されたときには、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。もっとも、民事上の請求権には消滅時効が存在します。
以下で、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間について解説します。
被害の事実と加害者を知ってから3年
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が「損害及び加害者を知ってから3年」で時効により消滅します(民法724条1号)。被害に気がついてから3年で請求権がなくなってしまうということです。
3年という期間は短く、刑事上の公訴時効よりも早く到来するおそれがあります。被害に気がついたらすぐに動かなければなりません。
横領時から20年
巧妙な手口であれば、横領行為からしばらく経った後で気がつくケースもあるでしょう。犯行に気がつかないまま時が過ぎても、行為時から20年を経過すると消滅時効にかかってしまいます(民法724条2号)。
とはいえ、刑事の7年に比べると長い期間です。被害に気がつかずに時が過ぎていったケースでは、刑事上の責任は問えなくても民事上の請求ができる可能性があります。
業務上横領の被害に気がついたらすぐに行動すべき
「自分のケースでは時効はまだ先だから、焦らなくて大丈夫」と考えてはなりません。時効期間にかかわらず、早めに行動するのが望ましいです。
最後に、被害に気がついたときにすべき行動について解説します。以下の記事でも詳しく説明していますので、あわせて参考にしてください。
参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
時効にならなくても証拠は消えていく
時効が先でも行動すべきなのは、証拠が時間の経過とともに消えていくためです。
加害者に法的責任を問うには、刑事であれ民事であれ証拠が不可欠です。証拠がないと、刑事で不起訴処分とされたり、民事で敗訴判決をくだされたりしてしまいます。
業務上横領の証拠になり得るものとしては、以下が挙げられます。
- 加害者の使用しているPCに残っている履歴
- 口座の入出金記録
- 取引先に渡した領収書
- 店舗の防犯カメラ映像
客観的証拠を集めるほか、関係者への事情聴取も必要です。加害者本人にバレないように、慎重に進めましょう。
従業員による横領が発生した際の証拠の集め方や注意点について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説
民事・刑事で責任を追及する
証拠が集まったら、本人に事情聴取を行い、反応によってとるべき手段を検討します。法的責任を追及するには、民事訴訟や刑事告訴が考えられます。
思いつきやすいのは民事訴訟による賠償請求ですが、効果的でないケースが多いです。勝訴したとしても、相手に財産がなければ強制執行ができません。横領では、加害者は得たお金をすぐに使ってしまいがちです。加害者に財産がなく実際に回収できなければ、勝訴判決は絵に描いた餅になってしまいます。
そこで考えられるのが刑事告訴です。刑事告訴は、犯罪被害を受けた事実と処罰を求める意思を捜査機関に伝える行為です。本来は刑罰を求めるために行いますが、処罰されるのをおそれた加害者が示談を申し出てくるケースがあります。示談のためにはお金を用意する必要があるため、親族などに借金をする加害者もいます。
結果的に、被害額を取り返すためには刑事告訴の方が有効なケースが多いです。なお、犯行に気がつくのが遅れて刑事の公訴時効期間を経過しているときでも、民事による請求ができる可能性はあります。
横領で刑事告訴するメリット・デメリットについて詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
懲戒処分も検討する
民事・刑事上の手段だけでなく、社内での懲戒処分も検討しましょう。
横領という犯罪行為がある以上、懲戒解雇が相当なケースが多いはずです。とはいえ、不当に懲戒解雇をすると、従業員が解雇無効を主張してトラブルが拡大するおそれがあります。就業規則の規定を確認したうえで、適正な手続きを踏んで行ってください。
業務上横領の被害に気がついたらすぐにリード法律事務所にご相談ください
ここまで、業務上横領の時効について解説してきました。
業務上横領の刑事上の時効期間は行為から7年、民事上の時効期間は気がついてから3年、行為から20年です。刑事・民事のいずれかの時効にかかっていても、他方の責任は追及できる可能性があるので諦めないでください。反対に時効がまだ先であっても、証拠が消える前に、被害に気がついたらすぐに行動しましょう。
業務上横領の被害を受けた方は、リード法律事務所までご相談ください。
刑罰を科すためにも、被害を取り返すためにも、刑事告訴は効果的です。しかし、刑事告訴に精通している弁護士はあまりいません。
当事務所は、犯罪被害者のために、横領も含めて刑事告訴を数多く受理させて参りました。民事上の請求だけでなく、刑事告訴に関する豊富な知識・経験・ノウハウを有しています。
業務上横領の加害者の責任を追及したい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。