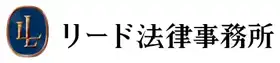経理担当者による横領は非常に多いです。
小口現金の抜き取り、口座からの不正送金・引き出し、領収書の偽造による不正請求など、様々な手口があります。お金を管理する立場にあるため犯行が容易であり、被害額は膨らみやすいです。
経理担当者による横領が発覚した際には、事実調査を行ったうえで、懲戒解雇、損害賠償請求、刑事告訴といった対応をとらなければなりません。
この記事では、経理担当者による横領の手口や発生しやすい理由、被害に遭った会社の対処法などを解説しています。経理担当者に横領されてお困りの方は、ぜひ最後までお読みください。
横領に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:【被害者向け】横領罪とは?類型と量刑、構成要件について解説
目次
経理担当者による横領・着服のパターン
経理担当者による横領には、多様なバリエーションがあります。単に小口現金を抜き取るだけの手口から、書類を偽造して不正を隠ぺいしようとする手口に至るまで様々です。
まずは、よくある事例を解説します。
参考記事:業務上横領の種類|よくある手口と対処法を被害者側弁護士が解説
小口現金の抜き取り
比較的単純なのは、小口現金の抜き取りです。管理が行き届いていない環境であれば多少の減少には気づかれないため、経理担当者が犯行に及んでしまいます。
たしかに、小口現金から抜き取れる金額は少ないかもしれません。しかし、何度も積み重なれば累計の被害額は大きくなります。横領に手を染めるきっかけになり、より大胆な他の手口に移行するケースもあるでしょう。たとえ少額でも厳しく対処する必要があります。
少額の横領について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領は少額でも成立する?被害者ができることを解説
会社口座からの不正送金・引き出し
会社口座からの不正送金や引き出しもよくある手口です。
たとえば、経理担当の権限を利用して会社口座から自身の口座に送金するケースがあります。加害者名義だと気づかれやすいため、知人や関係する会社の口座を利用する場合も多いです。送金ではなく、銀行のATMや窓口で引き出すケースもあります。
入出金履歴を経理担当者しか確認していない状況では、不正送金・引き出しが発生しやすいです。
書類偽造による不正請求
単に送金・引き出しをするだけでは発覚しやすく言い逃れも難しくなるため、書類の偽造を伴う場合もあります。架空の領収書・請求書・契約書等を作成し、正当な出金であるように装う手口です。
架空であるとはいえ体裁を整えた書面が存在しているため、表面上は問題がなく気がつかれにくくなります。チェック体制が十分でないと長期間にわたって行われ、被害額が莫大になってしまうケースも多いです。会社印を利用する場合もあります。
業務上横領罪だけでなく、会社名義を冒用しているケースなどでは私文書偽造罪も成立し得ます。私文書偽造罪については、以下の記事を参照してください。
参考記事:私文書偽造罪とは?刑事告訴した際の量刑と公文書との違い、事例を紹介
水増し請求させキックバック受領
取引先と協力する場合もあります。たとえば、本来の請求額よりも水増しした金額を取引先に請求させて会社から支払いを行い、上乗せ分をキックバックしてもらうようなケースです。上乗せ分を分配していれば、相手にもメリットがあります。
こうした犯行は、業務上横領罪ではなく、背任罪や詐欺罪に該当する可能性もあります。他者と協力している点で非常に巧妙かつ悪質な手口です。
違法なキックバックについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:従業員の違法キックバック・違法リベートは背任罪で刑事告訴できる?
切手や印紙の換金
管理を任されている切手や印紙を換金する手口もあります。
切手や印紙は、1枚ごとの金額は少ないものの、会社によっては大量に使用するでしょう。多数の切手・印紙を換金して得た金銭を懐に入れていれば、大きな被害になり得ます。
会社として切手や印紙の枚数を適切に管理できていないときは、経理担当者による不正が横行しやすいです。
経理担当者が横領する理由
経理担当者による横領は非常に発生しやすいです。理由としては以下が挙げられます。
- 犯行が可能な立場にある
- 発覚しづらい
- 会社のお金との意識が薄い
順に解説します。
参考記事:横領してる人の特徴は?会社が注意すべきポイントや対処法を解説
犯行が可能な立場にある
まず、経理担当者は犯行が可能な立場にある点が挙げられます。
そもそも業務上横領罪は、業務として管理を任された他人の財産を自分のものにする犯罪です。管理権限を付与された人しか犯行の主体になり得ません。
経理担当者は、金銭の管理全般を会社から任されており、お金を動かせる立場にあります。ひとたび魔が差すと、簡単に犯行ができてしまいます。
発覚しづらい
経理担当者による横領は発覚しづらいといえます。経理は担当者以外がタッチしていない場合も多く、経営者や他の従業員に知られずに実行可能であるためです。
特に中小企業で経理担当者がひとりだと、より犯行に及びやすいです。一般的に経理を任されているのは信頼の厚い従業員であり、他の従業員から疑われにくいでしょう。経理担当者は、信頼されている立場を利用して横領に手を染めるのです。
発覚しないと犯行が繰り返されやすいです。最初は少額でも次第にエスカレートし、気づいたときには会社に大きなダメージが生じているケースもよくあります。
会社のお金との意識が薄い
経理担当者は、一般の従業員と比較して金銭に触れる機会が段違いに多いです。日常的に金銭を扱っていると、会社のお金であるとの意識が薄れていく場合もあります。
他人のお金だと思うと簡単に使えませんが、自分のお金だと思うと使うハードルが下がるでしょう。誘惑に駆られてあっさり手を付けてしまいます。
会社に金銭管理を任されている立場にあることを忘れ、軽い気持ちで犯行に及んでしまうことも、経理担当者による横領が発生する原因のひとつです。
経理担当者による業務上横領への対処法
経理担当者が業務上横領をした際には、まず調査をして証拠を集めましょう。犯行を立証できるだけの証拠が集まったら、懲戒解雇、損害賠償請求、刑事告訴といった手段を検討します。
参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
事実調査・証拠収集
まずは調査を行い、犯行の証拠を集めてください。証拠はいかなる手段をとるにせよ不可欠です。
証拠になるものはケースバイケースですが、例としては以下が挙げられます。
- 預金通帳、帳簿
- 領収書、請求書、契約書
- メールの文面
他の従業員への事情聴取も有効ですが、共犯者がいる可能性もあるので注意しましょう。客観的な証拠の方がより重要です。
立証できるだけの証拠が揃った段階で、本人に事情聴取をしてください。先に事情を聴くと、否定されたときに追及できないうえに、証拠隠滅を図られるリスクが高いです。
横領の証拠の収集方法については、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説
証拠がなかったら?
たとえ証拠が手元になかったとしても、諦める必要はありません。弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、証拠になり得るものや収集・保全方法がわかります。弁護士のサポートを受けて十分な証拠が得られれば、責任追及が可能になります。
証拠がないときの対処法について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領の証拠がないならどうする?被害者がしてはいけないことは?
懲戒解雇
証拠が揃ったら、加害者にとる措置を検討します。考えられる方法のひとつが懲戒解雇です。
横領はれっきとした犯罪であり、懲戒解雇が妥当なケースがほとんどです。たとえ少額であったとしても、金銭管理を任される立場にある経理担当者による横領は、責任が非常に重いといえます。
他の従業員への抑止効果の観点からも、横領には解雇を基本とした厳しい処分を科すべきです。ただし、就業規則の規定を確認したうえで弁明の機会を与えるなど、手続きはしっかりと踏むようにしてください。
退職後に発覚したら?
経理担当者による横領は、退職して新たな担当者が就任した際に発覚する場合も多いです。退職後に判明したときは、事後的な懲戒解雇はできません。根拠規定があれば、退職金の(一部)返還を求めることは可能です。
犯行から時間が経つと、民事上の請求や刑事告訴もできなくなってしまいます。早めに行動するようにしましょう。
退職後に横領が発覚した際の対応について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:従業員の横領が退職後に発覚したら?対処法や時効について解説
損害賠償請求
会社が被った損害について、加害者に賠償請求ができます。まずは交渉により支払いを請求し、応じないときに訴訟を提起するのが一般的です。
もっとも、訴訟で勝訴できても、相手に十分な財産がなければ回収できません。横領に及ぶ加害者はお金に困っている場合が多く、横領で得たお金も使い切ってしまっている可能性があります。特に経理担当者による横領は金額が膨らみやすく、全額の回収は思いのほか困難です。
訴訟を提起して勝訴しても、実際にお金を受け取れないのであれば判決は絵に描いた餅になってしまいます。民事上の請求は多くの被害者が考える方法ですが、現実には期待通りの結果を得られる見込みは薄いです。
返済を受けやすいケースについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:横領されたお金は返ってくる?返済されやすいケースと方法を弁護士が解説
刑事告訴
刑事告訴をする方法もあります。刑事告訴とは、犯罪被害を受けた事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思を伝える行為です。
告訴を受けた警察には、捜査を進めて事件を検察に送致する義務が生じます。捜査されずに放置される可能性がある被害届と比べて、告訴状の提出は効果的な手段です。業務上横領罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」であり、被害額が大きいときは初犯でも実刑となり、直ちに刑務所に収監されます。
刑罰を科せるだけでなく、告訴をきっかけに支払いに応じるケースもあります。告訴を受けて刑罰を恐れた加害者が、会社に被害弁償をして示談してもらいたいと考えるためです。特に経理担当者が多額の横領をして実刑が予想されるケースでは、刑務所行きを避けるために返金するモチベーションが生じやすいです。加害者本人がお金を持っていなくても、親族などが肩代わりしてくれるケースもあります。
刑事告訴は、本来は刑罰を求めるための手段です。しかし結果的に、民事訴訟をせずとも金銭面の被害を回復できる可能性があります。
横領の刑事告訴について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
経理担当者による不正行為は弁護士にご相談ください
ここまで、経理担当者による横領について、よくある手口や犯行に及びやすい理由、事後的な対処法などを解説してきました。
経理担当者による、権限を利用した横領は後を絶ちません。小口現金の抜き取り、不正送金、架空請求など、様々なバリエーションがあります。被害を受けた際には、懲戒解雇、民事上の請求、刑事告訴といった対応が考えられます。
経理担当者に横領された方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所は犯罪被害者弁護を専門としており、民事上の返金請求だけでなく、刑事告訴にも強い弁護士事務所です。実際に、横領でも数多くの告訴を受理させて参りました。状況やご希望に応じて、様々な選択肢の中からベストな方法を選択して実行いたします。
経理担当者による横領にお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。