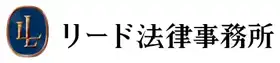「共同経営者(取締役)が横領をしているようだ」とお悩みではないですか?
共同経営者・取締役といった役員は、会社において強大な権限を有しています。権限を振りかざして会社の財産が不正に利用されると、莫大な損害が発生しやすいです。
行為態様によって、業務上横領罪、特別背任罪などの犯罪が成立します。証拠を収集したうえで、解任、損害賠償請求、刑事告訴といった手段をとるようにしましょう。
この記事では、共同経営者・取締役・役員によくある横領の手口や成立する犯罪、会社の対処法などを解説しています。役員の不正行為による被害を受けた会社経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。
横領に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:【被害者向け】横領罪とは?類型と量刑、構成要件について解説
目次
共同経営者・取締役による横領の特徴と事例
共同経営者・取締役は会社において強い権限を有しているため横領を実行しやすく、被害額も膨らみやすいです。手口には様々なバリエーションがあります。
まずは、役員による横領の特徴やよくある事例を解説します。
参考記事:横領してる人の特徴は?会社が注意すべきポイントや対処法を解説
権限が大きいため犯行が容易
そもそも業務上横領罪や特別背任罪は、会社から委託された職務上の権限を利用して行われる犯罪です。共同経営者や取締役は会社において様々な権限を付与されているため、犯行ができる立場にあります。
権限を有しているため、たとえば金銭の移動、経費支出などは簡単に行えてしまいます。一般の従業員とは異なり、上司からのチェックも働きません。役員ごとに担当がわかれていれば、担当部門については特に犯行がしやすいでしょう。
不正行為そのものは自身では行わず、他の従業員に命令して実行されるケースもあります。権限行使により、潜在的には様々な不正行為が可能な状況にあるといえます。
被害額が膨らみやすい
権限が強大である分、不正行為に及んだ際の被害額は膨らみやすいです。実際に、数千万円、数億円といった巨額の被害が発生するケースもあります。
一般の従業員であれば、想定される被害額が限られる場合も多いです。たとえば集金担当者による横領であれば、担当している集金額が被害の上限になります。
取締役は権限を利用すれば、金額の大きい契約や送金も可能です。気がつかれないのをいいことに犯行を繰り返せば、会社に甚大な損害を与えるおそれがあります。
多額の横領については、以下の記事でも解説しています。
参考記事:1000万円以上の業務上横領に遭ったら?会社がすべき対応を解説
よくある事例
共同経営者・取締役による横領・背任等の不正行為には様々なバリエーションが存在します。
具体例は以下の通りです。
- 会社口座から自身、自身が関わる別会社、親族、友人などの口座に送金する
- 経理担当者に指示して不正送金を実行させる
- 会社財産を自身・関係会社などの借金返済にあてる
- 経費と称して、会社のお金を私的な飲食費や遊興費にあてる
横領の手口については、以下の記事でも解説しています。
参考記事:業務上横領の種類|よくある手口と対処法を被害者側弁護士が解説
共同経営者・取締役による横領行為に成立する主な犯罪
一般的に「横領」と呼ばれる行為について成立し得る犯罪は様々考えられます。取締役が実行した場合には、業務上横領罪や特別背任罪が代表的です。他に、会社名義を使って契約書を作成した際の有印私文書偽造・行使罪など、別の犯罪も成立し得ます。
ここでは、業務上横領罪や特別背任罪について解説します。私文書偽造罪については、以下の記事を参照してください。
参考記事:私文書偽造罪とは?刑事告訴した際の量刑と公文書との違い、事例を紹介
業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務として管理を任された他人の財産を自分のものにする犯罪です。共同経営者・取締役が、権限を与えられた会社財産について、着服、使い込み、持ち逃げ、売却、贈与などをしたときに成立し得ます。
たとえば、会社のお金を私的な飲食費に流用したケースでは、業務上横領罪に該当すると考えられます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です(刑法253条)。「拘禁刑」とは、2025年6月に懲役刑と禁錮刑が一本化されたものであり、犯人を刑務所に収監する刑罰です。取締役の横領では被害額が大きくなりやすいため、初犯でも実刑判決が下されて直ちに刑務所に収監されるケースがよくあります。
業務上横領罪について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説
特別背任罪
特別背任罪とは、取締役など会社において重要な役割を担う人が、任務に背く行為をして会社に損害を与えたときに成立する犯罪です。取締役による任務違反行為は会社に与える損害が大きいため、通常の背任罪とは別に定められており、刑が重くなっています。
たとえば、友人の経営する破産寸前の会社に対し、友人を助けたいと考えた取締役が会社財産から代わりに借金返済をしたときは特別背任罪が成立します。
業務上横領罪と特別背任罪とは、他人から委託を受けた人が信頼を裏切るという点で似ています。両罪とも成立しそうな事例もありますが、先に横領を検討し、横領が成立しないときに背任の成否を検討するのが一般的です。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」「1000万円以下の罰金」「その両方」のいずれかです(会社法960条)。業務上横領罪と同様に、被害額が大きい場合には実刑判決が出て直ちに刑務所行きとなります。
特別背任罪について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:特別背任罪とは、構成要件・罰則や対象者、事例を紹介
取締役・役員が横領したときの対処法
取締役が横領したときには、まずは調査して証拠を収集しましょう。結果を踏まえて、解任、損害賠償請求、刑事告訴といった対応を検討します。
参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
事実調査・証拠収集
まずは事実を調査して証拠を集めましょう。いかなる対応をするにせよ、証拠は不可欠になります。
何が証拠になるかは、状況や手口に応じてケースバイケースです。たとえば、送金記録、契約書・領収書、メールの文面などが挙げられます。
他の取締役や従業員への事情聴取も効果的ですが、共犯者である可能性もあるので注意しなければなりません。裁判で重視される客観的証拠の方が、より重要です。
証拠を隠滅されるおそれがあるため、本人への事情聴取は証拠が揃った段階で最後に行うようにしましょう。
横領の証拠収集について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説
証拠がなかったら?
「証拠がない」という方もいらっしゃるでしょう。証拠がないとしても、すぐに諦める必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、証拠になり得るものや収集方法がわかります。弁護士のサポートを受けて証拠が見つかり、責任追及できるケースもあります。
証拠がないときの対処法は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:業務上横領の証拠がないならどうする?被害者がしてはいけないことは?
解任
不正行為を立証できるだけの証拠が揃ったら、どう責任追及するかを検討しましょう。考えられる方法のひとつが取締役の解任です。
株主総会において過半数が賛成すれば、取締役(役員)を解任できます(会社法339条1項)。
もっとも、「正当な理由」がないときには、解任により取締役に生じた損害を会社が支払わなければなりません(同条2項)。横領や背任が事実であれば「正当な理由」が認められます。しかし、不正の事実の証拠が不十分だと「正当な理由」が認められず、役員報酬などの支払い義務が生じます。
解任する前に、不正の立証ができるかを必ず確認しておきましょう。
損害賠償請求
会社が受けた被害につき、取締役に対して損害賠償請求ができます。
一般の従業員による被害であれば、不法行為(民法709条)等を根拠として請求しますが、役員が任務を怠ったことによる損害賠償については、会社法423条を根拠とした請求が可能です。交渉による支払いに応じなければ、訴訟により請求します。
しかし、たとえ裁判で勝訴できたとしても、相手に十分な財産がなければ現実には回収できません。強制執行が意味をなさず、判決が絵に描いた餅になってしまうのです。
横領に及ぶ加害者はお金に困っている場合が多いうえに、役員による横領は被害額が膨らみやすい傾向にあります。損害賠償請求を行っても、結局被害を全額は取り返せないケースが多いです。
参考記事:横領されたお金は返ってくる?返済されやすいケースと方法を弁護士が解説
刑事告訴
業務上横領罪や特別背任罪に該当するとして、刑事告訴する方法もあります。刑事告訴とは、犯罪被害を受けた事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思を伝える行為です。
社内での横領や背任は会社が申告しない限り発覚しづらく、告訴により警察・検察に伝える意味は大きいといえます。告訴を受けた警察には捜査を進めて検察に事件を送致する義務が生じるため、被害届の提出よりも強力な手段です。
加えて、告訴をきっかけとして賠償が進むケースもあります。告訴を受けた加害者が処罰をおそれ、被害弁償をして示談しようとするためです。被害額が大きく実刑判決が予想される場合には、刑務所行きを避けるために、より積極的に示談を進めようとするモチベーションが加害者側に生じます。本人に財産がなくても、親族などが肩代わりするケースがあります。
本来、告訴は刑罰を求めるための手段です。もっとも、結果的に民事訴訟を提起せずとも金銭面の被害を回復できる可能性があります。
横領による告訴について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
共同経営者・取締役・役員の横領が発覚したら弁護士にご相談ください
ここまで、共同経営者・取締役の横領について、よくある事例や成立する犯罪、会社がとれる対処法などを解説してきました。
役員は権限が強いため不正行為に及びやすく、被害は甚大になりやすいです。解任や損害賠償請求だけでなく、業務上横領罪や特別背任罪での刑事告訴も検討しましょう。
共同経営者・取締役・役員による横領被害にお悩みの方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所は犯罪被害者弁護を専門としており、民事上の損害賠償請求だけでなく、刑事告訴にも強い弁護士事務所です。実際に、横領でも数多くの告訴を受理させて参りました。状況やご希望に応じて、様々な選択肢の中からベストな方法を選択して実行いたします。
役員による横領にお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。