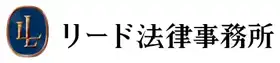「業務上横領」とひとくちに言っても、様々な種類があります。経理担当者による不正送金、集金した現金の着服、商品の横流しなど、手口は千差万別です。
社内での業務上横領に対応するには、よくある手口を知り被害を迅速に把握したうえで、適切な措置をとらなければなりません。
この記事では、業務上横領の典型的な種類・手口と被害に遭った際の対処法を解説しています。社内での横領に対応したい会社関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
そもそも業務上横領とは?
会社で横領が発生した場合、通常は業務上横領罪が成立します。もっとも、一般的に「横領」と考えられている行為であっても、不正を行った人の立場や行為態様によって、法律上は別の犯罪に該当する可能性もあります。
手口を紹介する前に、そもそも業務上横領罪とはいかなる犯罪か、他の罪との違いはどこにあるかを解説します。業務上横領罪の基礎知識については、以下の記事もご参照ください。
参考記事:業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説
業務上管理を任された財産を自分の物にする犯罪
業務上横領罪は、業務として管理を任されている他人の財産を、勝手に自分の物にする犯罪です。
会社の財産を管理している従業員だけでなく、運送業者やクリーニング業者のように客から財産を預かる立場の人が犯行主体になります。職業である必要はなく、サークルなどの団体で財産を管理している人も加害者になり得ます。
「横領」の典型例は着服であり、預かっている財産を自分の懐に入れるのがよくある事例です。他にも、使い込み、売却、質入れなど、本来であれば所有者でないとできないはずの行為をしていれば横領に該当します。
他の犯罪との違い
業務上横領罪は、他の犯罪と区別が難しい場合があります。他の犯罪との違いを見ていきましょう。
単純横領罪との違い
業務上横領罪とよく似た犯罪が単純横領罪です。両者の違いは、加害者が「業務上」財産を占有しているか否かです。
「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復または継続して行われる事務をいいます。他人の財産の管理を、一度限りではなく、繰り返しまたは続けて行うと予定されている人が横領行為に及べば、業務上横領罪が成立します。仕事として財産を管理している場合が典型例ですが、サークル活動のように、職業でなくても「業務」とされるケースがあります。
対して、単にプライベートで預かっていた財産を横領したときに成立するのが単純横領罪です。たとえば、友人から預かっていたゲームソフトを自分の物にしたり、転売したりするケースです。
法定刑は、単純横領罪が「5年以下の懲役」であるのに対し、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と重くなっています。業務上管理を任される財産はプライベートより大きくなりやすく、甚大な被害も想定されるため、刑が重くされています。
通常、会社内で横領が発生した際に問われるのは業務上横領罪です。横領罪の類型について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:【被害者向け】横領罪とは?類型と量刑、構成要件について解説
背任罪との違い
業務上横領罪との区別が難しいのが背任罪です。背任罪は、他人から職務を任された人が、任務に背く行為をして、職務を任せた人に損害を与える犯罪です。会社の取締役などが背任行為をすると、より刑が重い特別背任罪が成立します。
他人からの信頼を裏切る点で、横領と背任は共通します。
判例によると、両者の違いは経済的効果が誰に帰属するかです。加害者が経済的利益を得ると横領、加害者に直接の利益は生じずに会社に経済的損失が生じる場合には背任となります。
背任の典型例は、銀行の担当者が、返済が困難であると知りながら融資を実行するケースです。担当者自身に経済的な利益は帰属しないため、横領ではなく背任となります。
横領と背任の区別は難しい場合があります。加害者の法的責任を問う際には、弁護士に相談するとよいでしょう。背任罪について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:背任罪・特別背任罪とは?構成要件や横領罪との違いなど、事例付きで解説
窃盗罪との違い
業務上横領罪と窃盗罪との区別も難しいです。
窃盗罪は「他人が」占有している財産を盗む犯罪です。横領は「自分が」他人の財産を占有しているときに成立するのであり、両罪は財産を誰が占有していたかが異なります。
法律上の「占有」という概念は少し複雑ですが、加害者に財産の管理権限があるときは横領、ないときは窃盗と考えておけば概ね間違いありません。たとえば、店舗内の商品の管理権限を有する店長が商品を持ち帰れば業務上横領、管理権限のないアルバイトが持ち帰れば窃盗になります。
会社の財産を従業員が自分の物にしたときには、法律上は横領ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。横領と窃盗の違いについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:横領と窃盗の違いとは?具体例や被害者がすべきことを弁護士が解説
詐欺罪との違い
社内での不正行為が詐欺罪に該当するケースもあります。
詐欺罪は、他人から財産を騙し取る犯罪です。加害者が他人を欺く行為をして、騙された被害者が財産を交付すると成立します。
会社内では、金銭管理を任されていない従業員が、交通費の水増し請求、架空の経費請求などをしたときに詐欺罪が成立する可能性があります。同じ行為であっても、金銭の管理権限を任されている従業員がしていれば業務上横領罪です。
いずれの罪に該当するにせよ、不正である点に変わりはなく、厳しく対処する必要があります。詐欺罪について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:詐欺罪とは?量刑や詐欺手口の種類、被害に遭ったらすべきことを解説
業務上横領の種類・手口
業務上横領罪には、様々な種類が存在します。会社内で起きる業務上横領について、典型的な手口をご紹介します。
経理担当者による横領
非常に多いのが、経理担当者による横領です。経理担当者はお金に触れる機会が多く、誘惑に駆られやすいです。会社の金銭の流れをよく把握しているため、バレずに実行する方法を知っているともいえます。
たとえば、会社の口座から、自己名義の口座に送金するケースがあります。自己名義だと発覚した際に言い逃れできないため、別口座を利用する場合も多いです。
架空の請求書を発行して取引の実態があるように装うなど、気づかれないように様々な工作を行うことも可能であるため、判明するまで時間を要しやすいです。取引先と共謀して代金の水増し請求をさせて差額を受け取るなど、第三者を巻き込んでいるケースも存在します。口座への送金ではなく、現金を着服する場合もあります。
立場を利用して帳簿上は辻褄を合わせられるため、巧妙になりやすいのが経理担当者による横領です。特に中小企業で担当者がひとりの場合には発生しやすく、発覚が遅れて被害が甚大になるおそれもあります。被害を防ぐには、複数人でチェックできる体制にするのが望ましいです。
集金担当者による横領
集金担当者による横領もよくあります。集めたお金を着服する誘惑に駆られやすいためです。
典型的なのが、顧客・取引先から集めた現金を自分の懐に入れ、会社には未受領と報告するケースです。金額を偽って差額を着服する場合もあります。
店舗責任者による横領
店舗責任者が、立場を利用して横領に及ぶケースも見受けられます。
たとえば、店舗の売上を過少申告して差額を着服するケースです。レジの現金を持ち出す、商品を持ち逃げするといった事態も考えられます。
立場上数字の操作ができてしまい、発覚しづらい場合もあります。気がついたときには被害が膨らんでいるケースも少なくありません。
物品・在庫管理者による横領
金銭だけでなく、物を管理している人による横領も考えられます。
たとえば、会社の備品を管理する担当者による持ち出し、倉庫の在庫管理担当者による商品の転売などです。会社側が数量を正確に把握していないのをいいことに、犯行に及んでしまいます。
役員による横領
社長や役員による横領もあり得ます。強大な権限を有しており、誰にもバレずに犯行を実行しやすい立場にあるためです。
自身や関係者に不正に送金する、私的な支出を会社の経費とするなど、様々なパターンが存在します。場合によっては、横領ではなく背任(特別背任)になるケースもあります。
社長や役員による横領は、被害が甚大になりやすいとともに、会社全体に与える影響も大きいです。他の役員や従業員による監視の目が必要になります。
業務上横領が発覚した際の対処法
社内で業務上横領が発覚した際には、証拠を集めたうえで、とるべき手段を検討しなければなりません。
ここでは、業務上横領が判明したときの対処法を簡単に解説します。より詳しく知りたい方は、次の記事もお読みください。
参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説
証拠を集める
まずは、犯行の証拠を集めてください。証拠は、どんな手段をとるにしても必要になります。
特に重要なのが客観的証拠の収集です。何が証拠になるかはケースバイケースですが、例としては以下が挙げられます。
- 防犯カメラ映像
- 請求書、契約書、領収書などの書面
- 預金通帳など、金銭の動きがわかる記録
- メールの文面
客観的証拠のほか、関係者への事情聴取も行います。証拠隠滅や言い逃れを防ぐために、加害者本人への事情聴取は証拠が揃ってから、最後に実施しましょう。認める・認めないにかかわらず、事情聴取の内容は必ず記録に残してください。
横領の証拠収集方法について詳しくは、以下の記事で解説しています。
参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説
とるべき手段を検討する
証拠を集めたら、とるべき措置を検討してください。考えられるのは、社内での懲戒処分、民事上の返還請求、刑事告訴です。すべて行っても、一部だけでも構いません。
順に詳しく解説します。
懲戒処分
横領があった際には、社内で懲戒処分をしましょう。厳しい処分をしないと、他の社員に「横領は大きな問題ではない」と思われてしまいます。
横領という犯罪行為に至っている以上、大半のケースで懲戒解雇が相当です。ただし、不当解雇とされないために、就業規則に沿って進め、加害者の弁明も聴取するようにしてください。
民事上の請求
被害を取り戻すには、民事上の返還請求が考えられます。交渉や訴訟を通じて、被害額の返還を求めます。
しかし、実際には全額の回収は難しいケースが多いです。横領で得たお金は既に使い切ってしまい、手元にはないでしょう。たとえ勝訴判決を得ても、強制執行の対象にできる財産が十分になく、空振りに終わってしまうリスクが高いです。
民事上の返還請求は多くの方が考える手段ですが、特に被害額が大きい場合、現実には全額を取り戻すのは困難です。横領されたお金が返ってくるかについては、以下の記事をお読みください。
参考記事:横領されたお金は返ってくる?返済されやすいケースと方法を弁護士が解説
刑事告訴
刑事告訴する方法もあります。刑事告訴とは、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思を伝える行為です。
横領は隠れて行われる犯罪であるため、通常は捜査機関は気がついてくれません。告訴をすれば、被害が伝わり警察・検察が動いてくれるため、刑罰につながる可能性が高まります。業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。被害額が大きいなど悪質な事案では、実刑判決により直ちに刑務所に収監されるケースもあります。
加えて、告訴をきっかけとして被害を取り返せる場合も存在します。刑罰そのものや前科に伴う社会的・経済的不利益を避けるために、告訴された加害者が示談を申し入れてくるのです。示談の際には被害弁償について話し合われますが、本人は支払えなくても家族の援助を得てお金を用意するケースがあります。
告訴は、本来は刑罰を求める行為です。しかし結果的に、被害を取り返す可能性を高められるメリットもあります。横領で刑事告訴するメリットについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説
業務上横領の被害に遭ったら弁護士にご相談ください
ここまで、業務上横領罪の性質や、典型的な手口などを解説してきました。
業務上横領罪は、業務として管理を任されている他人の財産を、勝手に自分の物にする犯罪です。経理担当者、集金担当者、役員など、様々な立場の人が犯し得る犯罪といえます。発覚した際には、証拠を集めたうえで、とるべき措置を検討しなければなりません。
社内で業務上横領の疑いが生じた会社の関係者の方は、リード法律事務所までご相談ください。
当事務所は、犯罪被害者弁護に力を入れており、横領でも数多くの告訴を受理させて参りました。証拠収集から告訴状の作成、警察への提出、加害者との交渉に至るまで、被害者の皆様を徹底的にサポートいたします。
横領に限らず、背任・窃盗・詐欺など、社内で発生した犯行に対応いたします。被害に遭った方は、まずはお気軽にお問い合わせください。